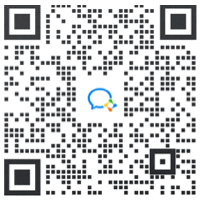目录
Content
Chapter_1
Chapter_2
Chapter_3
Chapter_4
Chapter_5
Chapter_6
Chapter_7
Chapter_8
Chapter_9
Chapter_10
Chapter_1
化物語(下)
西尾維新
化バケモノ物ガタリ語 下
西尾維新NISIOISIN
阿良々木《あららぎ》暦《こよみ》が直面する、完全無欠の委員長?羽川《はねかわ》翼《つばさ》が魅せられた「怪異」とは--!?
台湾から現れた新人イラストレーター、〝光の魔術師?ことVOFANとのコンビもますます好調! 西尾維新が全力で放つ、これぞ現代の怪異! 怪異! 怪異!
青春を、おかしく[#「おかしく」に傍点]するのはつきものだ!
BOOK&BOX DESIGN VEIA
FONT DIRECTION
SHINICHIKONNO
(TOPPAN PRINTING CO.,LTD)
ILLUSTRTION
VOFAN
本文使用書体:FOT-筑紫明朝ProL
第四話 なでこスネイク
第五話 つばさキャット
第四話 なでこスネイク
001
千石《せんごく》撫子《なでこ》は妹の同級生だった。僕には二人の妹がいて、千石撫子はその内、下の方の妹の友達だった。今現在の酷《ひど》い有様と違って、小学生の頃の僕は、それなりに普通に友達のいる子供だったのだが、それでもなんと言えばいいのだろう、みんなと遊ぶのは好きだが誰かと遊ぶのは好きではないという感じで、休み時間にクラスの連中と遊ぶことはあっても、放課後にクラスの連中と遊ぶことは、滅多になかった。嫌な子供だ。語るにつけ思い出すにつけ、嫌な子供だった。語りたくも思い出したくもない。まあ、三つ子の魂《たましい》百までというか、その逆と言うか、ただ単に、昔から僕はそういう奴だったと言うだけの話だ。そんなわけで、放課後は、特に習い事をしていたわけでもないのに、さっさと家に帰ることを常とする僕だったが、その帰った家に遊びに来ていたのが、千石撫子だったのである。今でこそ二人べったり、いつもいつでもいついつでもそばにいる、兄としては心配以上に気持ちの悪くなってしまうくらい仲のいい二人の妹ではあるが、小学生の頃は別々に行動することも多く、上の妹はもっぱらアウトドア派、下の妹はインドア派で、三日に一日は、下の妹は家に学校の友達を連れてきていた。千石撫子が特に妹と仲良しだったというわけではなく、たくさんいた妹の友達の中の一人だった感じなのだろう。『なのだろう』と、ここで語尾がいささか不確かになってしまうのは、正直言って僕がその頃のことをよく憶えていないからなのだが、そうは言っても、いざ思い出してみれば妹が家に連れてきた友達の中では、まだ千石撫子は印象に残っている方だ。それは何故なら、放課後、友達と遊ぶこともなく家に帰っていた僕は、妹の遊びに付き合わされることが多々あって(当時、二人の妹と僕は同室だった。僕が両親から自分ひとりの部屋が与えられたのは中学生になってからだ)、それは大抵の場合、人数合わせ、ボードゲームなどをするときの賑《にぎ》やかしということだったのだけれど、妹が千石撫子と遊ぶとき、僕にお呼びがかかる率が異様に高かったからである。要は、友達が多い妹が(これは今も変わらず、妹二人に共通して言えることなのだが、あの二人は人の中心に立つのが非常にうまい。兄としては非常に羨《うらや》ましい限りである)、家に連れてくる同級生としては、千石撫子は珍しく、一人で行動するタイプの少女だったということだ。はっきり言って妹の友達なんて誰でも同じに見えてしまうので、必然、一人で、誰ともまぎれずにいた彼女の名前くらいは、僕の記憶にも残っていたというわけなのである。
だが、名前くらいだ。
やはりよく憶えていない。
だからこれも語尾が曖昧《あいまい》になってしまって申し訳ない限りなのだが、千石撫子は、内気で、言葉少なで、俯《うつむ》いていることが多い子供--だったと思う。思うのだが、まあ、しかし、わからない。ひょっとしたらそれは、妹の他の友達の特徴だったかもしれない。あるいは当時の僕の友達の特徴だったかもしれない。そもそも、小学生の頃の僕は、妹が家に友達を連れてくることを非常に迷惑に、鬱陶《うっとう》しく思っていたのだ。ましてそれにつき合わされていた相手の、印象がよいわけがないのである。今にして思えば、友達の兄貴と遊ばねばならなかった、妹の友達たちの方がいい迷惑だったのではないかと思うが、いずれにせよあくまでも昔の話で、あくまでも小学生の感性だと、そう理解して欲しい。実際、僕が中学生になってからは、下の妹も、家に友達を連れてくることは少なくなり、あったとしても、僕を遊びに誘うことはなくなった。部屋が別になったからというのもあるだろうが、もっと別の理由もあるだろう。そんなものだ。大体、妹は二人とも、中学は私立に行ったから、人間関係のほとんどは、彼女達の小学校卒業時にリセットされたはずである。千石撫子が妹の同級生だったのは小学生の頃の話で、今はもう、そうではない。別々の学校だ。だから僕が千石撫子に最後に会ったのは、どんな贔屓《ひいき》目に見積もっても二年以上前、そして恐らくは六年以上前--ということになる。
六年。
人間が変わってしまうには十分な時間だ。
少なくとも、僕は自分のことを、すっかり変わってしまったと認識している。昔からそういう奴だったと言っても、やはり今と昔とでは違うのだ。小学校の卒業アルバムなど、今の僕は痛々しくて、とても見ていられない。小学生の感性がどうのこうのとつまらないことも言ったが、しかし、考えてみれば、僕は今の自分があの頃の自分よりも優れ、勝っているとはとても思えない。思い出は美化されるものだとは言っても、そう、痛々しくてとても見ていられないのは小学生の頃の僕ではなくて、小学生の頃の僕から見る、今の僕ではないのだろうか。いや、恥ずかしい限りだが、たとえば今このとき、小学生の頃の自分と道でばったり出会っても、お互いに自分の正面に立っているそれが自分自身だと、気付くことはないだろう。
それが悪いことなのかどうか分からない。
過去の自分に今の自分を誇れないこと。
しかしそんなことだってある。
誰だってそうかもしれない。
だから僕は、千石撫子と再会したとき、最初、それが誰なのか、わからなかった--彼女のことを思い出すまでに、少し時間が掛かってしまった。もしも僕がすぐに、そうでなくとももっと早く、彼女のことに気付いていれば--蛇に絡《から》まれた彼女に気付いていれば、この物語はひょっとするとあんな結末には辿《たど》り着かなかったのではないかと思うと、非常にやるせないのだが、そんな後悔は彼女に対しても怪異に対しても、きっと何の意味もない。今回の話をいきなり結末から言ってしまえば、どうやら千石撫子は、僕にとって、うろ覚えだった妹の友達から、決して忘れることのできないたった一人になってしまったと、そういうことらしい。
002
「阿良々木《あららぎ》先輩、待たせてしまって申し訳ない」
六月十一日、日曜日。
さすが体育会系というべきなのかどうなのか、午前十時五十五分、待ち合わせ時間のきっちり五分前に、待ち合わせ場所の、僕らの通う直江津《なおえつ》高校正門前に、僕の一つ下の後輩、元バスケットボール部のエース、神原《かんばる》駿河《するが》は勢いよく駆けてきて、勢い余ってジャンプ一番、僕の頭の上を軽く跳び越してから、着地し、振り向いて、右手を胸の前に、爽《さわ》やかな笑顔と共にそう言った。......僕も、高校三年生としては、そりゃそんなに背の高い方ではないと自覚しているのだけれど、自分よりもちっちゃい女の子に正面飛びで跳び越えられるような身長ではないはずだと思っていたのだが、その認識はどうやらここで改めなければならないようだった。
「いや、僕も今来たとこだよ。別に待ってない」
「なんと......私の精神に余計な負荷《ふか》をかけまいと、そんなみえみえの気遣いをされるとは、やはり阿良々木先輩は、気立てのよい方だな。生まれ持った度量が違う。三歩下がって見上げない限り、私ごときには阿良々木先輩のその全貌《ぜんぼう》がつかめそうもない。会って数秒でこうも私の心を打つとは、阿良々木先輩の器の大きさには本当に驚かされるばかりだ。一生分の尊敬を、私は阿良々木先輩のためだけに、どうやら費《つい》やさねばならないようだな。なんてことだろう、全く、お恨《うら》み申し上げるぞ」
「..................」
相変わらずだな、こいつは。
そしてみえみえの気遣いって言うな。
さりげない優しさには気付かない振り、だろ。
「今来たとこだってのは本当だよ。それに、たとえそうじゃなかったとしても、お前もまた待ち合わせの時間よりも先に来たんだから、僕に謝《あやま》る必要なんかない」
「いや、それは聞けんな。阿良々木先輩がなんと言おうと、阿良々木先輩より先にこの場にいられなかったというだけで、私が謝る理由としては十分だ。目上の人物の時間を無駄にするというのは、許されない罪悪だと私は思っている」
「別に目上じゃないだろ」
「年上の先輩なのだから目上であっている」
「あってるけどさ......」
それは、単に歳の問題だけなんだよなあ。
あるいは身長とか(物理的に目上)。
でもそれも軽く飛び越えられるくらいのものだし。
神原駿河--直江津高校二年生。
つい先月まで、バスケットボール部のエースとして、学校一の有名人、学校一のスターとして名を馳《は》せていた人物である。私立進学校の弱小運動部を入部一年目で全国区にまで導《みちび》いたとあっては、本人の否応《いやおう》にかかわらず、そうならざるを得ないだろう。中途半端な落ちこぼれ三年生であるこの僕など、本来ならば口も利《き》けない、どころか、それこそまさに影も踏めないような存在だったはずの、恐るべき下級生だ。ついこの間、左腕に怪我をしたという理由で、キャプテンの座を後輩に譲《ゆず》り、バスケットボール部を早期引退--そのニュースがどれだけ衝撃的に学校中に響《ひび》いたか、それは記憶に新しい。古びることさえ、ないだろう。
神原の左腕には。
今も、包帯がぐるぐるに巻かれている。
「そう」
と、神原は静かに言う。
「私はこの通り、引退した身だ。バスケットボールしか取《と》り柄《え》のなかった私が、学校に対して貢献できることなど何もない。だから阿良々木先輩も、私をそのように扱ってもらいたい」
「扱うってな......お前ってなんか、何事に対しても自信ありげな癖《くせ》に、微妙に自己評価低いところがあるよな。そういうこと言うもんじゃないよ。お前がバスケットボール部に対してやってきたことは、ちょっと早めに引退したくらいで、ぱっと消えてなくなることでもないだろうに」
早期引退したことを気に病んでいる--というわけでもないのだろうが、まあ実際、あんなこと[#「あんなこと」に傍点]があって、そのままの自分でいうという方が、無茶な話か。けれど、僕としては、やっぱり神原には、そんな、自分を卑下《ひげ》するようなことを、言って欲しくはなかった。
「ありがとう、阿良々木先輩。心遣い、痛み入るばかりだ。その気持ちだけは受け取っておく」
「言葉もきちんと受け取れ。じゃあ、まあ、行くか」
「うん」
言って、神原は素早く僕の左側に回り込み、実にナチュラルな動きで、僕の空いていた左手に、自分の右手を繋《つな》いだ。『手を繋いだ』というよりは、『指を絡めた』という感じだった。五指がそれぞれに、もつれあっている。そしてそのまま、僕の腕に自分の身体をぎゅっと、まるで抱きつくかのように、隙間なく密着させてくる。身長差の問題で、丁度僕の肘《ひじ》辺りに神原の胸が来て、神経が集中したその敏感な部位に、マッシュポテトのような感触が伝わってくる。
「いや、阿良々木先輩。それを言うならマシュマロのような感覚だろう」
「え!? 僕、今の馬鹿みたいなモノローグ、声に出していたのか!?」
「ああ、そうじゃないそうじゃない。安心してくれ、テレパシーで伝わってきただけだ」
「そっちの方がより問題じゃねえか! この辺りのご近所さん、全員に聞かれているってことになるぞ!」
「ふふふ。まあ見せつけてやればいいではないか。私も最早《もはや》、スキャンダルを気にする身ではなくなったわけだしな」
「にこにこ笑顔で僕と付き合っている奴っぽいこと言ってんじゃねえよこの後輩! 僕が付き合っている相手はお前じゃなくて、お前の尊敬する先輩だろうが!」
戦場《せんじょう》ヶ|原《はら》ひたぎ。
僕のクラスメイト。
にして、僕の彼女。
にして--神原駿河の、慕《した》う先輩である。
学校一の有名人、学校一のスターと、今も昔も何の取り柄もない平凡な学生との間を繋いだのは、彼女、戦場ヶ原の存在である。神原と戦場ヶ原は中学生の頃から先輩後輩の間柄で、まあ途中、色々あり、色々あって、色々あったのだけれど、今現在も、神原戦場ヶ原のヴァルハラコンビとして、仲良くやっている。神原は『尊敬する先輩の付き合っている相手』として、僕を一時期、ストーキングしていたことがあるのだ。
「大体、お前は元々、スキャンダルなんて気にしてなかっただろうが。ええい、離れろ」
「嫌だ。デートのときは手を繋ぐものだと、ものの本には書いてあったぞ」
「デート!? 一回でも言ったか、そんなこと!?」
「む?」
神原はとても意外そうに首を傾《かし》げる。
「そう言えば、言ってなかったかな。阿良々木先輩から誘いがあったというだけで舞い上がってしまい、よく話を聞いていなかったのだが」
「ああ......ずっと生返事だったもんな、お前......」
「しかし、阿良々木先輩。それはさすがにどうかと思うぞ。私もそれなりに性に開放的な方ではあるし、できる限り阿良々木先輩の意に添いたいと考えるが、デートも抜きでいきなり行為に及ぼうというのは感心できない。阿良々木先輩の将来が心配だ」
「行為には及ばないし心配にも及ばねえよ! 高校二年生が性に開放的とか言ってんじゃねえ!」
「まあしかし、ことここに至れば仕方あるまい。気は進まないが、乗り乗りかかった船だ」
「ノリノリなんじゃねえかよ!」
ふと、神原の格好を見る。
ジーンズにTシャツ、長袖のアウター。高級そうなスニーカー。日差しが強くなってきたということもあってか、頭には野球帽をかぶっていて、それがこのスポーツ少女にはやけに似合うが、しかしそれはまあいいとして。
「長袖長ズボンで来いって言ったのは、一応、守ってるみたいだが......」
しかし。
そのジーンズはお洒落《しゃれ》にもあちこちが破れているものだったし、Tシャツは丈が短くて、神原のくびれたウエストが惜しげなく晒《さら》されていた。過激というか、なんというか......無論《むろん》、日曜日にどんな格好をしようとも、それは個人個人の自由なのだけれど......。
「......本当に何も聞いていなかったんだな、お前」
「何がだ」
「僕ら、これから山に行くんだけど」
「山? 山で行為に及ぶのか」
「及ばない」
「ふむ、なかなか野性的で悪くないな。阿良々木先輩もなかなかどうして男らしい。私も乱暴にされるのは嫌いじゃないぞ」
「及ばねえっつってんだろ! 聞けよ!」
長袖長ズボンで来いというのは、山中で、虫やら蛇やらに対する用心だって、ちゃんと説明したはずなんだけどな......。それなのに、そんな隙間だらけの服じゃ、あまり意味がないような......。
「まあよい。阿良々木先輩が行く場所であれば、私はどこにでもついていくだけだ。阿良々木先輩についてくるなと言われようともな。たと
Content
Chapter_1
Chapter_2
Chapter_3
Chapter_4
Chapter_5
Chapter_6
Chapter_7
Chapter_8
Chapter_9
Chapter_10
Chapter_1
化物語(下)
西尾維新
化バケモノ物ガタリ語 下
西尾維新NISIOISIN
阿良々木《あららぎ》暦《こよみ》が直面する、完全無欠の委員長?羽川《はねかわ》翼《つばさ》が魅せられた「怪異」とは--!?
台湾から現れた新人イラストレーター、〝光の魔術師?ことVOFANとのコンビもますます好調! 西尾維新が全力で放つ、これぞ現代の怪異! 怪異! 怪異!
青春を、おかしく[#「おかしく」に傍点]するのはつきものだ!
BOOK&BOX DESIGN VEIA
FONT DIRECTION
SHINICHIKONNO
(TOPPAN PRINTING CO.,LTD)
ILLUSTRTION
VOFAN
本文使用書体:FOT-筑紫明朝ProL
第四話 なでこスネイク
第五話 つばさキャット
第四話 なでこスネイク
001
千石《せんごく》撫子《なでこ》は妹の同級生だった。僕には二人の妹がいて、千石撫子はその内、下の方の妹の友達だった。今現在の酷《ひど》い有様と違って、小学生の頃の僕は、それなりに普通に友達のいる子供だったのだが、それでもなんと言えばいいのだろう、みんなと遊ぶのは好きだが誰かと遊ぶのは好きではないという感じで、休み時間にクラスの連中と遊ぶことはあっても、放課後にクラスの連中と遊ぶことは、滅多になかった。嫌な子供だ。語るにつけ思い出すにつけ、嫌な子供だった。語りたくも思い出したくもない。まあ、三つ子の魂《たましい》百までというか、その逆と言うか、ただ単に、昔から僕はそういう奴だったと言うだけの話だ。そんなわけで、放課後は、特に習い事をしていたわけでもないのに、さっさと家に帰ることを常とする僕だったが、その帰った家に遊びに来ていたのが、千石撫子だったのである。今でこそ二人べったり、いつもいつでもいついつでもそばにいる、兄としては心配以上に気持ちの悪くなってしまうくらい仲のいい二人の妹ではあるが、小学生の頃は別々に行動することも多く、上の妹はもっぱらアウトドア派、下の妹はインドア派で、三日に一日は、下の妹は家に学校の友達を連れてきていた。千石撫子が特に妹と仲良しだったというわけではなく、たくさんいた妹の友達の中の一人だった感じなのだろう。『なのだろう』と、ここで語尾がいささか不確かになってしまうのは、正直言って僕がその頃のことをよく憶えていないからなのだが、そうは言っても、いざ思い出してみれば妹が家に連れてきた友達の中では、まだ千石撫子は印象に残っている方だ。それは何故なら、放課後、友達と遊ぶこともなく家に帰っていた僕は、妹の遊びに付き合わされることが多々あって(当時、二人の妹と僕は同室だった。僕が両親から自分ひとりの部屋が与えられたのは中学生になってからだ)、それは大抵の場合、人数合わせ、ボードゲームなどをするときの賑《にぎ》やかしということだったのだけれど、妹が千石撫子と遊ぶとき、僕にお呼びがかかる率が異様に高かったからである。要は、友達が多い妹が(これは今も変わらず、妹二人に共通して言えることなのだが、あの二人は人の中心に立つのが非常にうまい。兄としては非常に羨《うらや》ましい限りである)、家に連れてくる同級生としては、千石撫子は珍しく、一人で行動するタイプの少女だったということだ。はっきり言って妹の友達なんて誰でも同じに見えてしまうので、必然、一人で、誰ともまぎれずにいた彼女の名前くらいは、僕の記憶にも残っていたというわけなのである。
だが、名前くらいだ。
やはりよく憶えていない。
だからこれも語尾が曖昧《あいまい》になってしまって申し訳ない限りなのだが、千石撫子は、内気で、言葉少なで、俯《うつむ》いていることが多い子供--だったと思う。思うのだが、まあ、しかし、わからない。ひょっとしたらそれは、妹の他の友達の特徴だったかもしれない。あるいは当時の僕の友達の特徴だったかもしれない。そもそも、小学生の頃の僕は、妹が家に友達を連れてくることを非常に迷惑に、鬱陶《うっとう》しく思っていたのだ。ましてそれにつき合わされていた相手の、印象がよいわけがないのである。今にして思えば、友達の兄貴と遊ばねばならなかった、妹の友達たちの方がいい迷惑だったのではないかと思うが、いずれにせよあくまでも昔の話で、あくまでも小学生の感性だと、そう理解して欲しい。実際、僕が中学生になってからは、下の妹も、家に友達を連れてくることは少なくなり、あったとしても、僕を遊びに誘うことはなくなった。部屋が別になったからというのもあるだろうが、もっと別の理由もあるだろう。そんなものだ。大体、妹は二人とも、中学は私立に行ったから、人間関係のほとんどは、彼女達の小学校卒業時にリセットされたはずである。千石撫子が妹の同級生だったのは小学生の頃の話で、今はもう、そうではない。別々の学校だ。だから僕が千石撫子に最後に会ったのは、どんな贔屓《ひいき》目に見積もっても二年以上前、そして恐らくは六年以上前--ということになる。
六年。
人間が変わってしまうには十分な時間だ。
少なくとも、僕は自分のことを、すっかり変わってしまったと認識している。昔からそういう奴だったと言っても、やはり今と昔とでは違うのだ。小学校の卒業アルバムなど、今の僕は痛々しくて、とても見ていられない。小学生の感性がどうのこうのとつまらないことも言ったが、しかし、考えてみれば、僕は今の自分があの頃の自分よりも優れ、勝っているとはとても思えない。思い出は美化されるものだとは言っても、そう、痛々しくてとても見ていられないのは小学生の頃の僕ではなくて、小学生の頃の僕から見る、今の僕ではないのだろうか。いや、恥ずかしい限りだが、たとえば今このとき、小学生の頃の自分と道でばったり出会っても、お互いに自分の正面に立っているそれが自分自身だと、気付くことはないだろう。
それが悪いことなのかどうか分からない。
過去の自分に今の自分を誇れないこと。
しかしそんなことだってある。
誰だってそうかもしれない。
だから僕は、千石撫子と再会したとき、最初、それが誰なのか、わからなかった--彼女のことを思い出すまでに、少し時間が掛かってしまった。もしも僕がすぐに、そうでなくとももっと早く、彼女のことに気付いていれば--蛇に絡《から》まれた彼女に気付いていれば、この物語はひょっとするとあんな結末には辿《たど》り着かなかったのではないかと思うと、非常にやるせないのだが、そんな後悔は彼女に対しても怪異に対しても、きっと何の意味もない。今回の話をいきなり結末から言ってしまえば、どうやら千石撫子は、僕にとって、うろ覚えだった妹の友達から、決して忘れることのできないたった一人になってしまったと、そういうことらしい。
002
「阿良々木《あららぎ》先輩、待たせてしまって申し訳ない」
六月十一日、日曜日。
さすが体育会系というべきなのかどうなのか、午前十時五十五分、待ち合わせ時間のきっちり五分前に、待ち合わせ場所の、僕らの通う直江津《なおえつ》高校正門前に、僕の一つ下の後輩、元バスケットボール部のエース、神原《かんばる》駿河《するが》は勢いよく駆けてきて、勢い余ってジャンプ一番、僕の頭の上を軽く跳び越してから、着地し、振り向いて、右手を胸の前に、爽《さわ》やかな笑顔と共にそう言った。......僕も、高校三年生としては、そりゃそんなに背の高い方ではないと自覚しているのだけれど、自分よりもちっちゃい女の子に正面飛びで跳び越えられるような身長ではないはずだと思っていたのだが、その認識はどうやらここで改めなければならないようだった。
「いや、僕も今来たとこだよ。別に待ってない」
「なんと......私の精神に余計な負荷《ふか》をかけまいと、そんなみえみえの気遣いをされるとは、やはり阿良々木先輩は、気立てのよい方だな。生まれ持った度量が違う。三歩下がって見上げない限り、私ごときには阿良々木先輩のその全貌《ぜんぼう》がつかめそうもない。会って数秒でこうも私の心を打つとは、阿良々木先輩の器の大きさには本当に驚かされるばかりだ。一生分の尊敬を、私は阿良々木先輩のためだけに、どうやら費《つい》やさねばならないようだな。なんてことだろう、全く、お恨《うら》み申し上げるぞ」
「..................」
相変わらずだな、こいつは。
そしてみえみえの気遣いって言うな。
さりげない優しさには気付かない振り、だろ。
「今来たとこだってのは本当だよ。それに、たとえそうじゃなかったとしても、お前もまた待ち合わせの時間よりも先に来たんだから、僕に謝《あやま》る必要なんかない」
「いや、それは聞けんな。阿良々木先輩がなんと言おうと、阿良々木先輩より先にこの場にいられなかったというだけで、私が謝る理由としては十分だ。目上の人物の時間を無駄にするというのは、許されない罪悪だと私は思っている」
「別に目上じゃないだろ」
「年上の先輩なのだから目上であっている」
「あってるけどさ......」
それは、単に歳の問題だけなんだよなあ。
あるいは身長とか(物理的に目上)。
でもそれも軽く飛び越えられるくらいのものだし。
神原駿河--直江津高校二年生。
つい先月まで、バスケットボール部のエースとして、学校一の有名人、学校一のスターとして名を馳《は》せていた人物である。私立進学校の弱小運動部を入部一年目で全国区にまで導《みちび》いたとあっては、本人の否応《いやおう》にかかわらず、そうならざるを得ないだろう。中途半端な落ちこぼれ三年生であるこの僕など、本来ならば口も利《き》けない、どころか、それこそまさに影も踏めないような存在だったはずの、恐るべき下級生だ。ついこの間、左腕に怪我をしたという理由で、キャプテンの座を後輩に譲《ゆず》り、バスケットボール部を早期引退--そのニュースがどれだけ衝撃的に学校中に響《ひび》いたか、それは記憶に新しい。古びることさえ、ないだろう。
神原の左腕には。
今も、包帯がぐるぐるに巻かれている。
「そう」
と、神原は静かに言う。
「私はこの通り、引退した身だ。バスケットボールしか取《と》り柄《え》のなかった私が、学校に対して貢献できることなど何もない。だから阿良々木先輩も、私をそのように扱ってもらいたい」
「扱うってな......お前ってなんか、何事に対しても自信ありげな癖《くせ》に、微妙に自己評価低いところがあるよな。そういうこと言うもんじゃないよ。お前がバスケットボール部に対してやってきたことは、ちょっと早めに引退したくらいで、ぱっと消えてなくなることでもないだろうに」
早期引退したことを気に病んでいる--というわけでもないのだろうが、まあ実際、あんなこと[#「あんなこと」に傍点]があって、そのままの自分でいうという方が、無茶な話か。けれど、僕としては、やっぱり神原には、そんな、自分を卑下《ひげ》するようなことを、言って欲しくはなかった。
「ありがとう、阿良々木先輩。心遣い、痛み入るばかりだ。その気持ちだけは受け取っておく」
「言葉もきちんと受け取れ。じゃあ、まあ、行くか」
「うん」
言って、神原は素早く僕の左側に回り込み、実にナチュラルな動きで、僕の空いていた左手に、自分の右手を繋《つな》いだ。『手を繋いだ』というよりは、『指を絡めた』という感じだった。五指がそれぞれに、もつれあっている。そしてそのまま、僕の腕に自分の身体をぎゅっと、まるで抱きつくかのように、隙間なく密着させてくる。身長差の問題で、丁度僕の肘《ひじ》辺りに神原の胸が来て、神経が集中したその敏感な部位に、マッシュポテトのような感触が伝わってくる。
「いや、阿良々木先輩。それを言うならマシュマロのような感覚だろう」
「え!? 僕、今の馬鹿みたいなモノローグ、声に出していたのか!?」
「ああ、そうじゃないそうじゃない。安心してくれ、テレパシーで伝わってきただけだ」
「そっちの方がより問題じゃねえか! この辺りのご近所さん、全員に聞かれているってことになるぞ!」
「ふふふ。まあ見せつけてやればいいではないか。私も最早《もはや》、スキャンダルを気にする身ではなくなったわけだしな」
「にこにこ笑顔で僕と付き合っている奴っぽいこと言ってんじゃねえよこの後輩! 僕が付き合っている相手はお前じゃなくて、お前の尊敬する先輩だろうが!」
戦場《せんじょう》ヶ|原《はら》ひたぎ。
僕のクラスメイト。
にして、僕の彼女。
にして--神原駿河の、慕《した》う先輩である。
学校一の有名人、学校一のスターと、今も昔も何の取り柄もない平凡な学生との間を繋いだのは、彼女、戦場ヶ原の存在である。神原と戦場ヶ原は中学生の頃から先輩後輩の間柄で、まあ途中、色々あり、色々あって、色々あったのだけれど、今現在も、神原戦場ヶ原のヴァルハラコンビとして、仲良くやっている。神原は『尊敬する先輩の付き合っている相手』として、僕を一時期、ストーキングしていたことがあるのだ。
「大体、お前は元々、スキャンダルなんて気にしてなかっただろうが。ええい、離れろ」
「嫌だ。デートのときは手を繋ぐものだと、ものの本には書いてあったぞ」
「デート!? 一回でも言ったか、そんなこと!?」
「む?」
神原はとても意外そうに首を傾《かし》げる。
「そう言えば、言ってなかったかな。阿良々木先輩から誘いがあったというだけで舞い上がってしまい、よく話を聞いていなかったのだが」
「ああ......ずっと生返事だったもんな、お前......」
「しかし、阿良々木先輩。それはさすがにどうかと思うぞ。私もそれなりに性に開放的な方ではあるし、できる限り阿良々木先輩の意に添いたいと考えるが、デートも抜きでいきなり行為に及ぼうというのは感心できない。阿良々木先輩の将来が心配だ」
「行為には及ばないし心配にも及ばねえよ! 高校二年生が性に開放的とか言ってんじゃねえ!」
「まあしかし、ことここに至れば仕方あるまい。気は進まないが、乗り乗りかかった船だ」
「ノリノリなんじゃねえかよ!」
ふと、神原の格好を見る。
ジーンズにTシャツ、長袖のアウター。高級そうなスニーカー。日差しが強くなってきたということもあってか、頭には野球帽をかぶっていて、それがこのスポーツ少女にはやけに似合うが、しかしそれはまあいいとして。
「長袖長ズボンで来いって言ったのは、一応、守ってるみたいだが......」
しかし。
そのジーンズはお洒落《しゃれ》にもあちこちが破れているものだったし、Tシャツは丈が短くて、神原のくびれたウエストが惜しげなく晒《さら》されていた。過激というか、なんというか......無論《むろん》、日曜日にどんな格好をしようとも、それは個人個人の自由なのだけれど......。
「......本当に何も聞いていなかったんだな、お前」
「何がだ」
「僕ら、これから山に行くんだけど」
「山? 山で行為に及ぶのか」
「及ばない」
「ふむ、なかなか野性的で悪くないな。阿良々木先輩もなかなかどうして男らしい。私も乱暴にされるのは嫌いじゃないぞ」
「及ばねえっつってんだろ! 聞けよ!」
長袖長ズボンで来いというのは、山中で、虫やら蛇やらに対する用心だって、ちゃんと説明したはずなんだけどな......。それなのに、そんな隙間だらけの服じゃ、あまり意味がないような......。
「まあよい。阿良々木先輩が行く場所であれば、私はどこにでもついていくだけだ。阿良々木先輩についてくるなと言われようともな。たと
看了又看
暂无推荐
验证报告
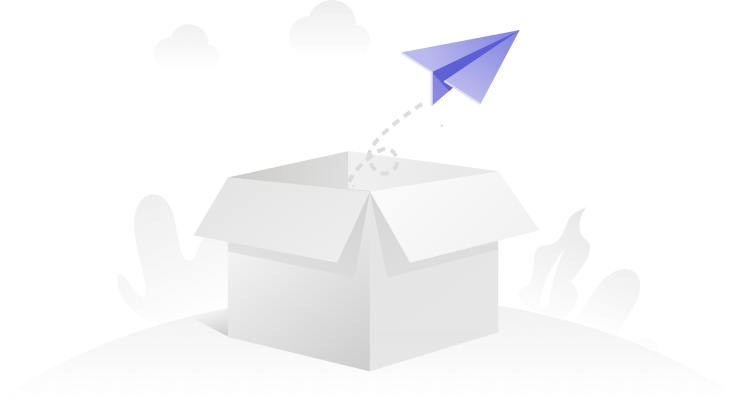
目前该文件尚无匹配的数据质量验证程序。我们将在后续版本中提供相应的验证支持,敬请谅解。

化物语(下)
1.47MB
申请报告